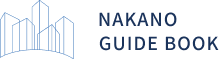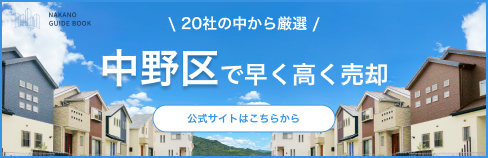不動産売却によって発生する譲渡所得税の負担に対しては、ふるさと納税制度を上手に活用することで、翌年の住民税や所得税の軽減が期待できます。
特に高額な不動産を売却する際には、所得が一時的に増加するため、寄附上限額も大幅に上がり、ふるさと納税の効果を最大限に引き出せるチャンスとなります。返礼品を受け取りながら地域貢献もできるため、実質的な節税につながる点が魅力といえるでしょう。
本記事では、不動産売却とふるさと納税の併用や計算方法、活用にあたっての注意点をわかりやすく解説します。不動産売却を控えている方は、ぜひ最後までご覧いただき、節税を実現するためのヒントにしてください。
なお、以下では中野区でおすすめの不動産会社を紹介しているので、あわせて参考にしてください。
不動産売却とふるさと納税は併用できる?

不動産を売却した年に、ふるさと納税を併用することは可能です。不動産を売却すると譲渡所得が発生し、一定の税金が課せられますが、これによって所得全体が増加し、ふるさと納税で控除される限度額も上がります。その結果、ふるさと納税でより多くの寄附を行い、住民税や所得税の一部を控除することが可能です。
ただし、不動産売却そのものがふるさと納税によって直接節税できるわけではありません。ふるさと納税は、翌年に支払う住民税・所得税から控除される仕組みであり、不動産売却で生じた税金の負担を減らす制度ではない点に注意が必要です。
不動産売却により一時的に大きな所得が生じた場合、その年の所得水準をもとにふるさと納税の控除枠が大きくなるため、返礼品を受け取りながら実質2,000円の負担で税額の一部を調整できるメリットがあります。売却による収入をふるさと納税に一部活用することで、翌年の納税額を抑えることが可能です。
ふるさと納税の仕組み
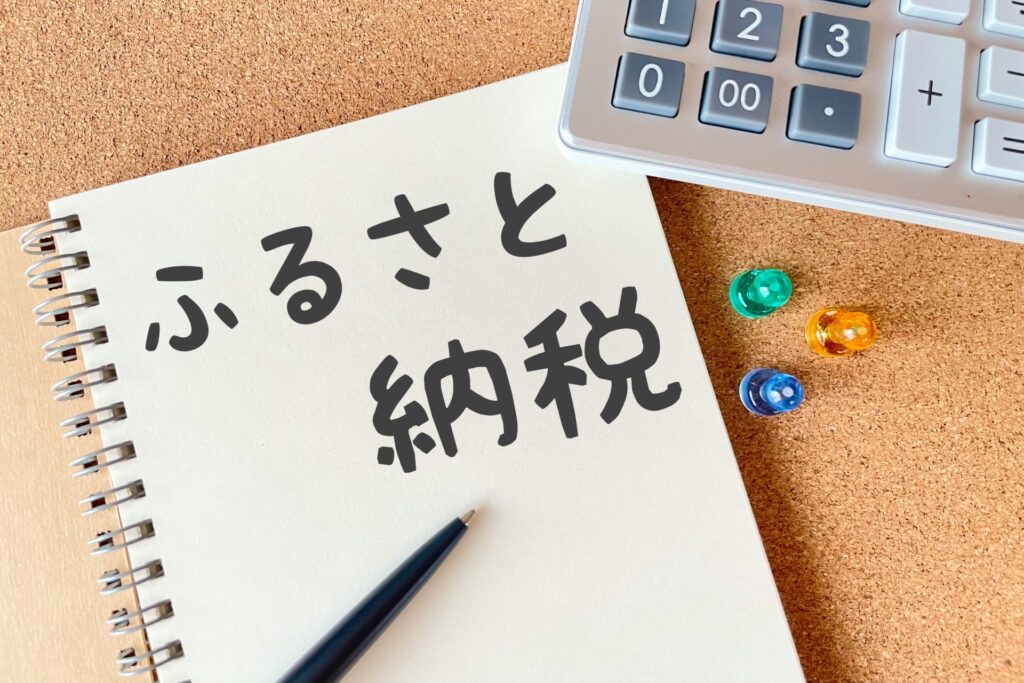
ふるさと納税とは、自治体に寄附を行い、一部が翌年の住民税や所得税から控除される制度です。寄附した金額のうち2,000円を超える部分については、一定の上限までは税額から控除されます。
ふるさと納税の特徴は、控除される金額がその年の「所得額」に応じて変動する点です。したがって、不動産を売却して一時的に所得が増加する年は、ふるさと納税の効果がより高まるタイミングといえるでしょう。
ただし、不動産売却で譲渡所得が発生する年は確定申告が必須のため、それと同時にふるさと納税の申告を行うことで、スムーズに控除を受けることが可能です。
ふるさと納税の上限額が引き上げられる条件

ふるさと納税の控除額には、年収や家族構成、給与以外の所得などを基に計算される上限があります。不動産売却によって得られる譲渡所得も課税対象に含まれるため、その年の総所得が大幅に増えることで、ふるさと納税の控除上限額も引き上げられます。
なお、譲渡所得は取得費や譲渡費用を差し引いた金額であるため、実際の課税所得額を正確に把握したうえで、ふるさと納税の寄附額を決定することが大切です。
不動産売却後にふるさと納税が適切なケース

ふるさと納税はどのタイミングでも行える寄附制度ですが、特に不動産売却を行った年に活用することで、高い節税効果を得られるケースがあります。具体的には、以下の4つのケースが適切です。
それぞれのケースについて解説していきます。
売却益により課税所得が増加した場合
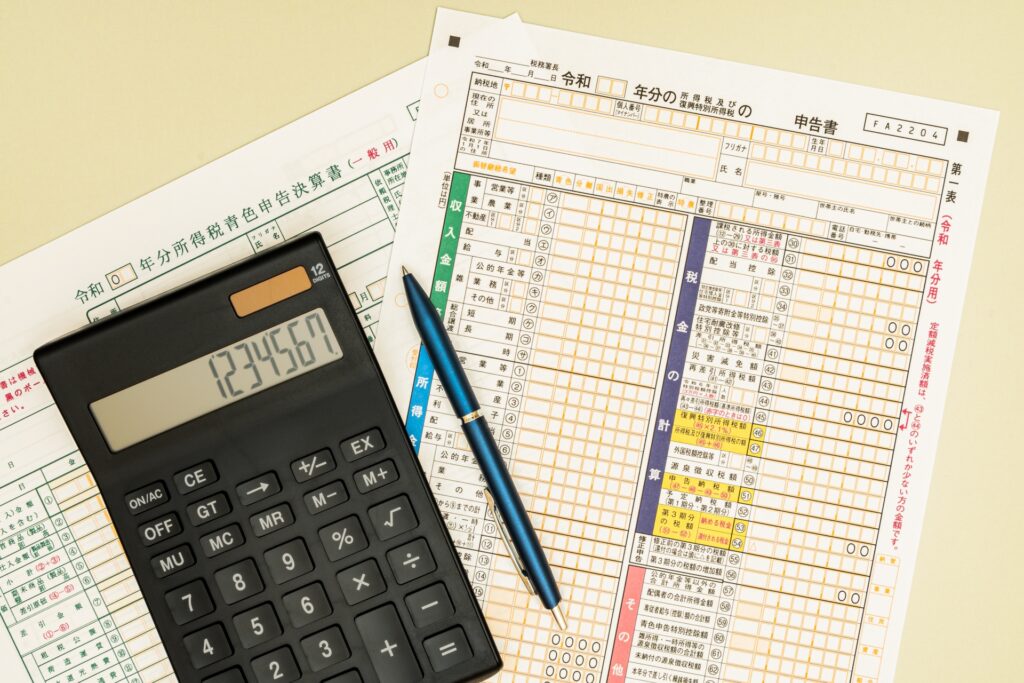
不動産売却により譲渡益が発生すると、給与などの他の所得と合算され、課税所得が大幅に増加します。このような場合、ふるさと納税の寄附上限額も比例して上がるため、より多くの寄附を行うことが可能です。
たとえば、通常の年収では5万円程度の上限だった方でも、不動産売却によって数十万円の控除が可能になることがあります。この増加分を利用してふるさと納税を行えば、税額控除を受けつつ、各自治体からの返礼品も受け取れるため、実質負担を最小限に抑えながら有効な節税が実現できるでしょう。
住民税の負担を翌年度に軽減したい場合

不動産売却によって課税所得が上昇すると、翌年の住民税が増額されることがあります。ふるさと納税は、この住民税の一部を軽減する効果があるため、翌年度の税負担を軽減したい方にとっては有効な手段です。
特に住民税は前年の所得に応じて課税されるため、不動産売却を行った年にふるさと納税を活用することで、翌年の負担を計画的に軽減できます。不動産の売却を検討している方は、早めにシミュレーションを行い、適切な寄附額を見極めましょう。
不動産の取得費が不明な場合

不動産の取得費が不明な場合、税務上は「概算取得費」として譲渡価格の5%しか認められません。この場合、本来よりも大きな譲渡所得が算出され、想定以上の税金が課される可能性があります。
このような状況においては、ふるさと納税を活用し、翌年の住民税や所得税の一部を控除し、少しでも税負担を軽減する対策が効果的です。取得費の証明が困難で、譲渡所得が高くなってしまった場合でも、ふるさと納税によって一部の税額を補うことができるため、結果的に負担軽減につながります。
節税の特例が利用できない場合
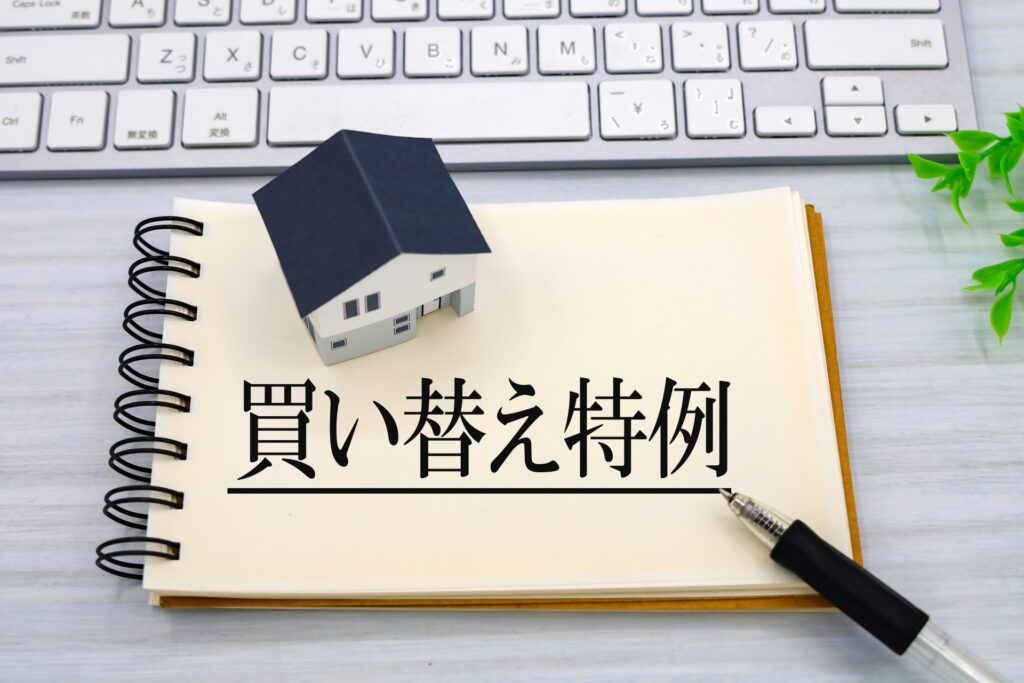
不動産売却では、「3,000万円特別控除」や「居住用財産の軽減税率」などの特例が適用されることがあります。しかし、適用要件を満たせない場合や、投資用物件・相続不動産などに該当するケースでは、特例の恩恵を受けられません。
このようなケースにおいても、ふるさと納税を活用することで、翌年の住民税・所得税を一部控除し、トータルでの税負担を軽減することが可能です。特例が使えない分、ふるさと納税を利用して補填する選択肢もあります。
不動産売却の譲渡所得額を計算する方法
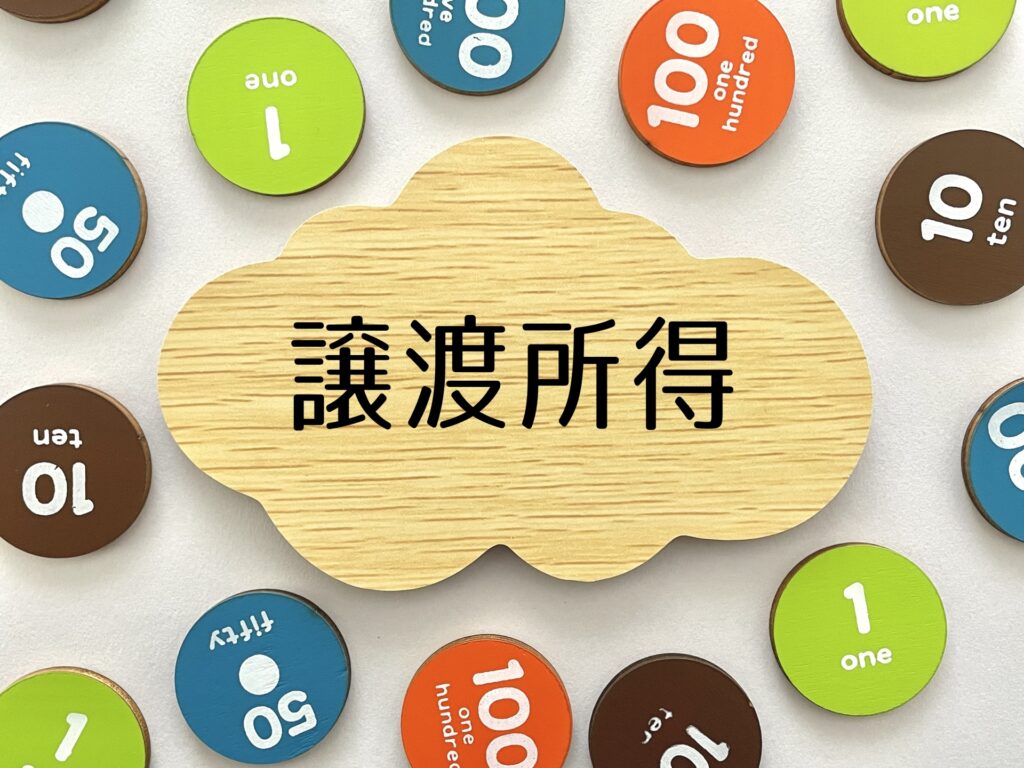
不動産を売却した際に発生する譲渡所得は、所得税や住民税の課税対象となるため、正確な計算が重要です。譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
譲渡所得=譲渡価格(売却額)-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
譲渡価格とは、実際に不動産を売却した金額を指します。取得費は、その不動産を購入した際の価格に加え、仲介手数料や登記費用などの関連経費を含めたものです。譲渡費用には、売却時に発生する仲介手数料、測量費、建物解体費用などが含まれます。
譲渡所得が大きい場合は税負担が増えますが、ふるさと納税の控除上限も高くなるため、節税が期待できます。一方で、取得費の証明ができないと所得が過大に計算されるため、領収書や契約書類は必ず保管しておきましょう。
ふるさと納税の控除上限額を計算する方法
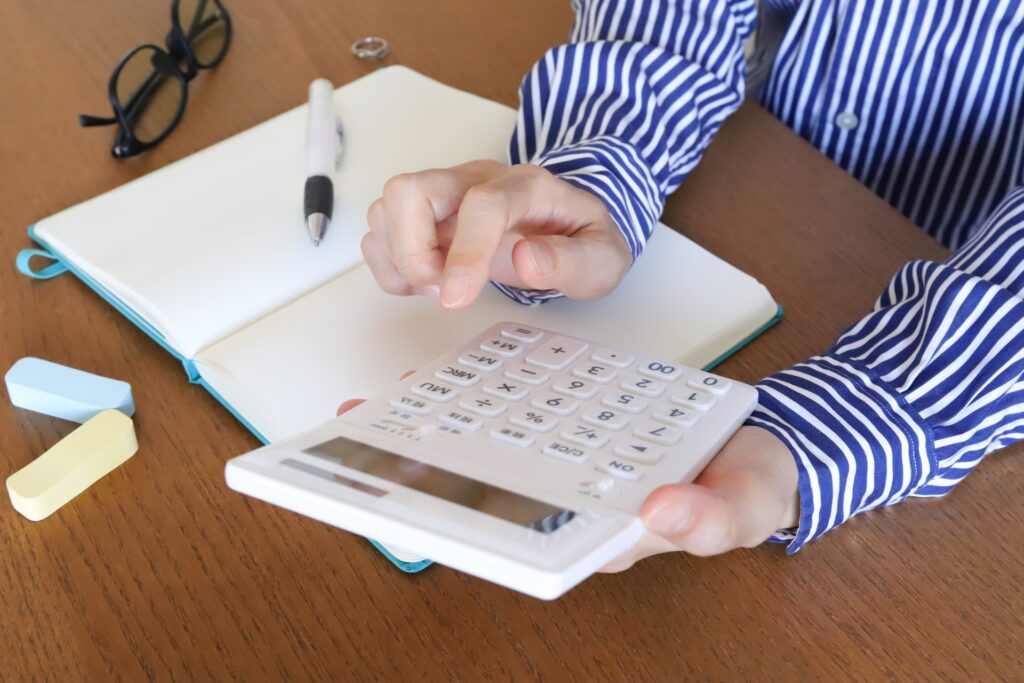
ふるさと納税を活用して節税するためには、事前に上限額の目安を把握しておく必要があります。控除上限額の計算には、「住民税所得割額」の把握が前提となります。具体的には、以下の流れで控除上限額を算出可能です。
それぞれの計算方法について解説していきます。
住民税所得割額を計算する

住民税は「均等割」と「所得割」に分かれており、控除上限額の計算に使われるのは後者の所得割額です。これは前年度の課税所得に応じて算出されるため、不動産の売却によって所得が増加すると、その年の所得割額も高くなります。
住民税所得割額は、以下のような計算式で求められます。
所得割額=(課税所得×税率10%)- 各種控除
課税所得とは、給与所得や譲渡所得などの合算から、基礎控除や扶養控除、社会保険料控除などを差し引いた金額です。譲渡所得がある場合は、その分も合算して計算されます。
確定申告を行うことで、実際に住民税所得割額が記載された通知書を翌年に受け取ることが可能です。売却予定の不動産がある場合は、譲渡所得を試算し、所得割額の目安を計算しておくことで、ふるさと納税の寄附額を設定できます。
ふるさと納税の控除上限額を算出する
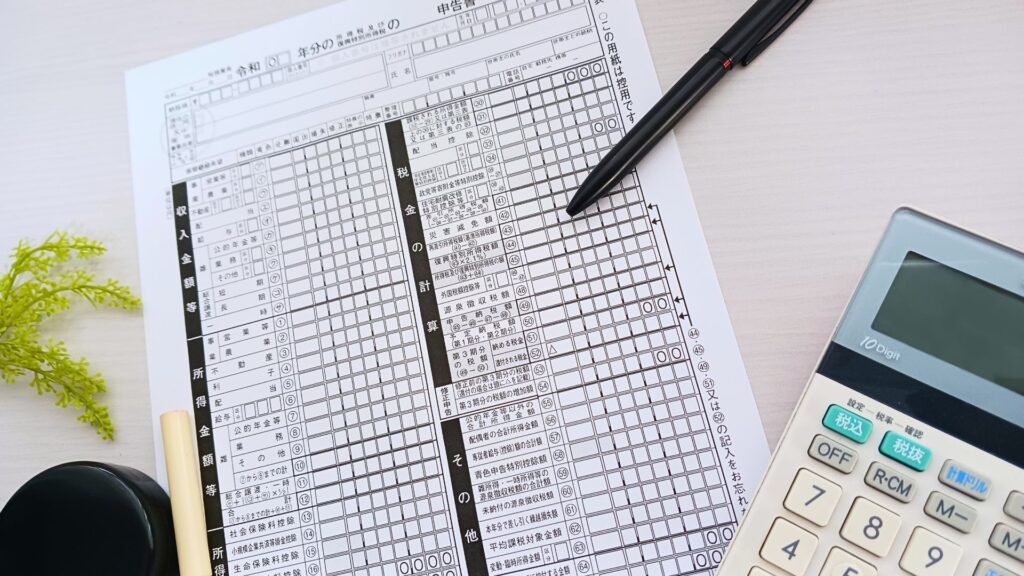
住民税所得割額が把握できたら、ふるさと納税の控除上限額を算出します。基本的な計算式は以下の通りです。
控除上限額= 住民税所得割額×20%+所得税の控除分 – 2,000円
住民税所得割額にかける20%、控除可能な住民税の割合の上限を示しており、実際の数値は家族構成や収入状況によって若干前後します。たとえば、住民税所得割額が60万円の場合、最大で12万円程度のふるさと納税が控除対象となる可能性があります。
ただし、所得税からの控除分もあるため、正確に上限額を知りたい場合は、以下のサイトにある「ふるさと納税 控除上限額シミュレーション」を活用するのがおすすめです。
不動産売却でふるさと納税を活用する際の注意点

不動産売却とふるさと納税を併用することで、節税のメリットを受けられる可能性がありますが、活用時にはいくつかの注意点があります。売却益によって課税所得が増える年は、税額もふるさと納税の上限も大きく変動するため、適切な手続きが重要です。
不動産売却時にふるさと納税を行う際の注意点としては、以下の4つが挙げられます。
それぞれの注意点について解説していきます。
ワンストップ特例が使えないケースがある
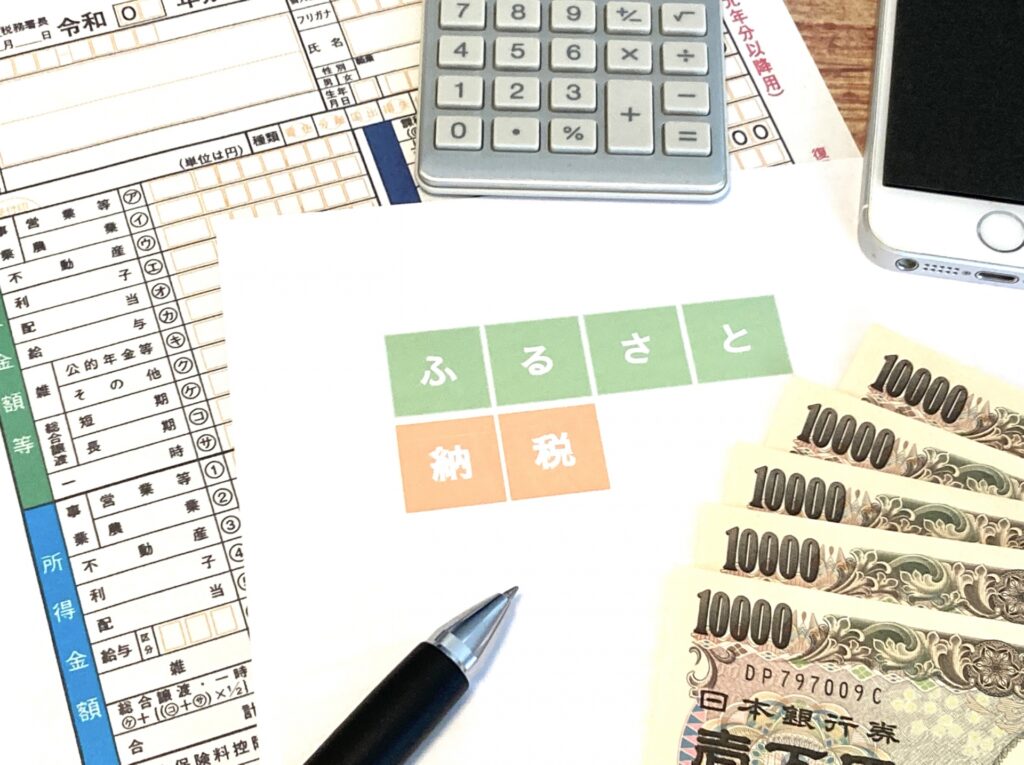
ふるさと納税を行う際、確定申告をしなくても控除を受けられる「ワンストップ特例制度」は、簡単に控除を利用できる制度です。しかし、ワンストップ特例制度は不動産売却を行う年には原則として利用できません。理由としては、不動産の売却によって譲渡所得が発生する場合、確定申告が必須となる点が挙げられます。
ワンストップ特例制度は、給与所得者などが確定申告をしないことを前提に設けられた制度であり、確定申告を行った時点で自動的に無効となります。そのため、不動産を売却する年にふるさと納税を行う場合は、寄附先の自治体が5つ以内であっても、確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載することが必要です。
ワンストップ特例制度における、確定申告についての誤認による控除漏れに注意しましょう。
住民税の控除は翌年の住民税から反映される

ふるさと納税による控除は、その年の納税額を直接減らすものではなく、寄附を行った翌年の住民税・所得税に反映される点に注意が必要です。例えば、2025年にふるさと納税を行った場合、その控除は2026年の住民税・所得税に適用されます。
このタイムラグを把握していないと、節税効果を実感できるまでに時間がかかるでしょう。特に不動産を売却した直後は、譲渡所得による税負担が重く感じられるかもしれませんが、ふるさと納税による税控除の恩恵は、あくまで翌年に受け取る形になります。
そのため、不動産売却による納税スケジュールとふるさと納税の控除時期を整理し、資金計画を立てたうえで寄附額を決定することが重要です。
年間合計で寄附した金額から2,000円を差し引いた部分が控除対象

ふるさと納税は、「実質2,000円の自己負担」と言われますが、これは誤解を招くこともある表現です。実際には、年間を通じて寄附した合計金額のうち、2,000円を差し引いた部分が所得税および住民税から控除されるという仕組みになっています。
例えば、合計10万円のふるさと納税を行った場合、自己負担は2,000円で済み、98,000円分が控除対象となります。ただし、控除には上限額が設定されているため、その上限を超えた寄附分については控除されません。
不動産売却で所得が増える年は、控除上限も高くなる一方、過剰に寄附をすると控除されない部分が発生するリスクもあります。そのため、シミュレーションを活用して適正な寄附額を見極めることが大切です。
損失となった場合でも確定申告は必要

不動産を売却した結果、譲渡損失が発生した場合でも、原則として確定申告は必要です。損失が生じた場合には税金が発生しないため、ふるさと納税の控除上限額にも影響します。所得が減ることで控除枠が狭まり、当初予定していた控除額を満たせないこともあります。
また、譲渡損失が住宅ローン控除と組み合わせて繰越控除の対象となるケースもあり、その場合でも確定申告が必要です。ふるさと納税の控除もこの申告に含める形になるため、損失が出た年でも正確な申告を怠らないようにしましょう。
損失が出たことによって、控除対象外になるふるさと納税が発生するリスクもあるため、損益見通しを早い段階で確認し、寄附額を調整することが大切です。
中野区でおすすめの不動産会社3選

不動産売却を成功させるには、地域に精通した信頼できる不動産会社に依頼することがポイントです。特に中野区は、エリアごとに相場やニーズが異なるため、地域密着型の実績ある会社を選ぶことで、的確な査定とスムーズな売却が期待できます。
以下では、中野区に強く、実績豊富な3つの不動産会社を紹介します。いずれも売主の目線に立った提案やサポート体制が整っており、初心者でも安心して相談できる会社です。
それぞれの会社について解説していきます。
中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社)

中野区不動産売却相談センターは、地元密着型のリヴウェル株式会社が運営する専門窓口です。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 中野区不動産売却相談センター(リヴウェル株式会社) |
| 住所 | 〒164-0003東京都中野区本町4-48-17 新中野駅上プラザ2階 |
| 設立年月日 | 令和3年2月24日 |
| 資本金 | 6,050万円 |
| 電話番号 | 03-6382-4223 |
| 公式HP | https://riv-ere.com/baikyaku-nakano-fudousan |
中野区エリアの物件売却に特化しており、地域特性を踏まえた査定や提案に定評があります。相続や住み替えといった相談にも対応しており、初めて売却を検討する方でも安心して任せられる点が魅力です。
特徴としては、不動産売却に特化したサイトを運営していることが挙げられます。中野区の過去の成約事例や価格動向なども公開しており、売却に関する判断材料を得やすいのが強みです。
なお、以下の記事では中野区不動産売却相談センターの口コミ・評判を詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。
また、詳しい情報は公式HPでも確認できます。ぜひ、チェックしてください。
オークラヤ住宅 新宿支社(オークラヤ住宅株式会社)

オークラヤ住宅は、首都圏全域に拠点を持つ大手不動産会社であり、新宿支社は中野区を含む都心西部エリアをカバーしています。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | オークラヤ住宅株式会社 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー12F |
| 設立年月日 | 昭和57年11月15日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 電話番号 | 0120-958-045 |
| 公式HP | https://www.ohkuraya.co.jp/ |
大手ならではのネットワークと広告展開力が強みで、購入希望者とのマッチング精度も高く、早期売却を目指すことも可能です。売却活動中の状況報告も丁寧で、進捗管理がしやすい点も評価されています。
また、無料の個別相談会や税理士・司法書士との連携による専門的なアドバイスも受けられるため、不動産売却にまつわる不安をトータルで解消できるサポート体制が整っています。
また、以下の記事では、オークラヤ住宅(新宿支社)について書いているので参考にしてください。
すみふの仲介 中野営業センター(住友不動産ステップ)

住友不動産グループの「すみふの仲介」は、全国展開する不動産仲介ブランドで、中野営業センターは中野駅北口から徒歩圏内に位置しています。
| 項目 | 詳細 |
| 会社名 | 住友不動産ステップ |
| 住所 | 〒164-0001 東京都中野区中野2-24-11 ナカノサウステラ2階 |
| 設立年月日 | 1975年3月1日 |
| 資本金 | 29億7000万円 |
| 電話番号 | 0120-832-842 |
| 公式HP | https://www.stepon.co.jp/ |
中野区全域の戸建て・マンション・土地売却に幅広く対応しており、グループの総合力を活かした安心のサポートが特徴です。売却査定から販売戦略の提案、買主との交渉まで一貫して担当者が対応するため、きめ細かいサービスを受けることができます。
売却時のホームインスペクション(建物調査)やリフォーム相談など、売主の不安を軽減するための体制も整っており、サポートの手厚さを重視する方におすすめです。また、豊富な成約実績に基づく査定と、住友不動産グループの信頼性が売主から高く評価されています。
以下の記事ではすみふの仲介(中野営業センター)について書いているので、参考にしてください。
まとめ

不動産を売却する際は、ふるさと納税を併用することで、翌年の住民税や所得税の負担を軽減できる可能性があります。売却によって一時的に所得が増加した場合は、ふるさと納税の控除上限額が引き上げられ、通常よりも多くの寄附を行えるチャンスとなります。
これから不動産売却を予定している方は、まず自身の譲渡所得額を計算し、住民税所得割額の目安を確認しましょう。その上で、ふるさと納税のシミュレーションを活用し、上限内で効率的な寄附計画を立てることが大切です。
節税効果を最大限に引き出したい場合は、税理士や不動産の専門家に相談しながら進めることで、失敗のない対策が可能です。将来の税負担を見据えたうえで、ふるさと納税を上手に活用し、計画的に不動産売却を進めていきましょう。